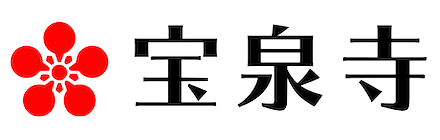
〒920-0836 金沢市子来町57
電話 076-252-3319
高野山真言宗 宝泉寺
通称「五本松」(ごほんまつ)
\ 宝泉寺は、ココ! /

護摩には、火天(かてん)への供養が護摩には欠かせません。
護摩は、火天の供養なくしてはじまりません。とても大切な仏天です。
火天は火を象徴化した神、アグニ。その成立はインド古代神話とともに、きわめて古いものです。
密教では、十二天や胎蔵曼荼羅、金剛界曼荼羅の外院にあって、老いた仙人のような姿であらわされています。(金剛界内院の守護にあたる四大神の一人でもあります。)
インドではヴェーダの時代より火をまつる祭式がおこなわれていました。お供えものを供養するにあたって、ただふつうに神々にお供えするだけではなく、これを火の中に投げ入れて、火の神を媒介として天上の神々に運んで供養するというものです。
このようなヴェーダの火の祭式を密教に取り入れ、これを浄化し、よりいっそう精神化して、密教特有のものへと発展させます。
火を焚いて焼くことには違いありませんが、密教ではその意味合いが大いに異なります。
インド在来の火まつり(護摩)の形に即して、これを密教化し、護摩に用いる火が、そのまま大日如来の智慧の火であるとするのです。
さらにはある観法を経て、護摩をとりまく環境も護摩の火も修行者も大日如来とほかならないと観じ、私たちの迷いや煩悩など、あらゆるマイナスの要因を焼き尽くします。
ここが、密教の護摩たる特質を発揮するところです。
護摩法は、物欲を満たすためや欲望の実現を目指して拝むのではなく、修行者の内心にある煩悩を焼き払って浄化して、さとりへの修行を進めることをの主たる目的としているのです。
その原動力となるのが、大日如来の智慧の火。すなわち火天です。
火天(かてん)
〔仏〕(梵語 Agni)十二天の一つ。もと古代インドの火神。仏教に入って護法神となり、胎蔵界曼荼羅では外金剛部院に配されて南東方を守護し、苦行仙の姿をし火焰の中に坐す。密教で護摩を修する時はこの天を勧請する。阿耆尼(あぎに)。火仙。火光尊。(『広辞苑』第七版)
ヴェーダ(Veda) 吠陀
(明・文・知などと訳す)インド最古の宗教文献。バラモン教の根本聖典。インドの宗教・哲学・文学の源流をなすもので、その起源は前1500年頃インドの北西方に移住したアーリア人が多数の自然神に捧げた賛美に発し、以来1000年の間に成立。最古のリグ(Ṛg)、それに次ぐサーマ(Sāma)・ヤジュル(Yajur)および異系統のアタルヴァ(Atharva)を四ヴェーダという。韋陀。(『広辞苑』第七版)
護摩法におけるファーストステージ、それが火天を供養する段。「火天段(かてんだん=第1段)」です。
ここでの観想は、「自身 即 火天 即 大日如来の智慧の火」という火天観につきます。
自分自心を空っぽにして、火天の三昧になりきって、護摩に没頭するのです。
そのときはじめて、護摩の火がそのまま大日如来の智慧の火となり、火天になりつくすのです。
護摩一座の本体が、ここにあります。
私が護摩を焚いているのだと、おごりが少しでも見えたら、それは火天の護摩ではありません。
迷いや煩悩を焼き尽くすことは不可能です。
大日如来(だいにちにょらい)
金剛頂経の中心尊格。その光明が遍(あまね)く照らすところから遍照(へんじょう)または大日という。大日経系の胎蔵界と金剛頂経系の金剛界との2種の像がある。遍照如来。遍照尊。遮那教主。(『広辞苑』第七版)

火天は、年老いた仙人の姿で、左第1手の5指を施無畏(せむい)ポーズをとり、第2手に数珠をとる。右第1手には仙人がもつ杖をとり、第2手に軍持(ぐんじ)をもち、火炎につつまれ、牛に座わっています。

「千と千尋の神隠し」の中で、湯屋(油屋)の釜場でボイラーを担当する老人が登場します。釜爺(かまじい)です。クモのような姿で、6本の手を自在に操り、「油屋」で使われる湯を沸かし、薬湯の薬を調合していました。火を扱うプロフェッショナル。火天と同じように、立派なヒゲを蓄えています。部下(眷属)に釜に石炭を運ぶススワタリがいましたね。
ひょっとしたら、釜爺のモデルは火天では? 映画をみたときから、私はそう思っています。
余談はさておき、胎蔵曼荼羅最外院にも火天とその眷属たちが描かれています。それぞれ、仙人と天女(后)がなかよくカップルで並んでいます。
火天の眷属の尊名には諸説があるようですが、ひとまずあげておきます。


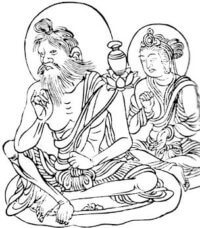

護摩法の観法は、壮大なイメージの世界です。座って拝めば拝むほど、深まってゆきます。
 まりちゃん
まりちゃん火の取り扱いはむつかしい。
うまく扱えるまで苦行を強いられから、
火の神様は老練な仙人のお姿なのかな。

あわせて目を通していただきたい記事がたくさんあります。


