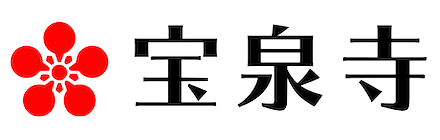
〒920-0836 金沢市子来町57
電話 076-252-3319
高野山真言宗 宝泉寺
通称「五本松」(ごほんまつ)
\ 宝泉寺は、ココ! /

 まりちゃん
まりちゃん護摩木をつくる原木を伐る日
決まってるのかな?
 住職
住職決まってるよ!
法の定め。
 まりちゃん
まりちゃんえっ?! まじ..
 住職
住職おつくりいただいた護摩木を一本のこらず焚きあげ、
護摩で生じた功徳をみんなの利益のために回向いたします。
他者のために汗を流す、みなさまの菩薩行に感謝です。
護摩木となる原木を伐り出す日
大切な護摩修行を行うにあたって、「年初めの甲子(きのえね)の日をもって護摩木を伐る」という規定が定められています。
下記の記事は、2020年(令和2)3月22日に護摩木をつくる原木を伐りに行ったときの様子が紹介されています。あわせてご覧ください。ちょうど新春二度目の甲子日でした。
もっとも当山では、降雪で伐り出した原木を搬出しにくいので、新春二度目の甲子に伐ることにしています。
3月22日、今春2度目の「甲子」に木を伐ってきました。
大切な護摩修行にあたって、「年初めの甲子(きのえね)の日をもって護摩木を伐ること」に定められていますが、北陸の当山では積雪を避け、新春2度目の甲子日を選んで木を伐ることに決めています。
甲子(きのえね)
甲子は干支の第一番目。甲が木性、子が水性で相生(水生木)の関係にあり、また、干支の組合せの一番目であることから、甲子の日は吉日とされています。たいへんめでたい日というわけです。
甲子日に護摩木を伐るという決まりがある以上、法に従いたいと思います。とはいえ一人で山に入って木を伐って、護摩木を作って、毎日護摩修法するのは至難なこと。お手伝いくださる有志のお力添えがあって、はじめて可能になります。本当にありがたいです。
 まりちゃん
まりちゃんコロナウイルス蔓延中。超こわい! だけど萎縮ばかりしていたら、元気な人まで調子が狂う。こういうときこそ、創造的なことに打ち込む時間をもちたい! あっ、マスクと手洗い、うがい。忘れずにね。
さわやかですね。ご縁をいただいたお山には、清らかな氣が満ちていました。
山主である保田さんの許可を得て、しっかりおまいりをしたあと、伐るべき木を実際に見て選ばせていただきました。今回は、樹齢三十数年とおもわれる、幹に枝の少ないまっすぐなスギをセレクト。細いけれど、節が無い! ぜいたくだなぁ〜
そのあとお山を守っている神さまとご先祖さま、保田さんを囲んで、クルーズのママさんお手製弁当をいただきました。
保田さん・ママさん・長谷川さん・森さん・羽場さん、ありがとうございました!
伐り出す前に、現場周辺の樹木の枝打ちをします。伐った木をスムーズに倒すための工夫です。
保田さん・長谷川さん・森さん・羽場さん、お世話になりました。
森さんがチェーンソーのプラグを交換し、長谷川さんが道具の積み込みにきてくれました。
すぐさま「おまいり」です。
安全第一。あわてず、ゆっくり、ていねいに!
トラックに積みやすい長さに伐りそろえ、根元に印をつけて搬出します。

帰山後、規定のサイズに輪切り、皮をむいて保管。乾燥を待ちましょう。
皮をむけば、つるつる。ほぼ節が無いから、たくさん乳木がとれますね!

保田さん・松田さん・高村さん・長谷川さん・森さん・羽場さん、おつかれさまでした。
ゴールデンウィークに、乾燥した切り株にクサビを打ち込んで荒割りしていきます。
朝からいいお天気なので、墨をつけました。
一人でやっていたところに、長谷川さんがおまいりにこられ、手伝っていただきました。

 住職
住職お店で購入すれば事足りる護摩木を、あえて自分たちで作ることで、より多くの気づきをいただけます。拝むだけが護摩ではありません。弘法さまの密教文化をいまに伝え育み生かす工夫。忘れてはいけません。
 まりちゃん
まりちゃん護摩木を自分で作って拝む行者さん
いま何人くらいいるのかな..
 住職
住職人様のことはよくわからない
護摩木づくりは自分との戦いだよ